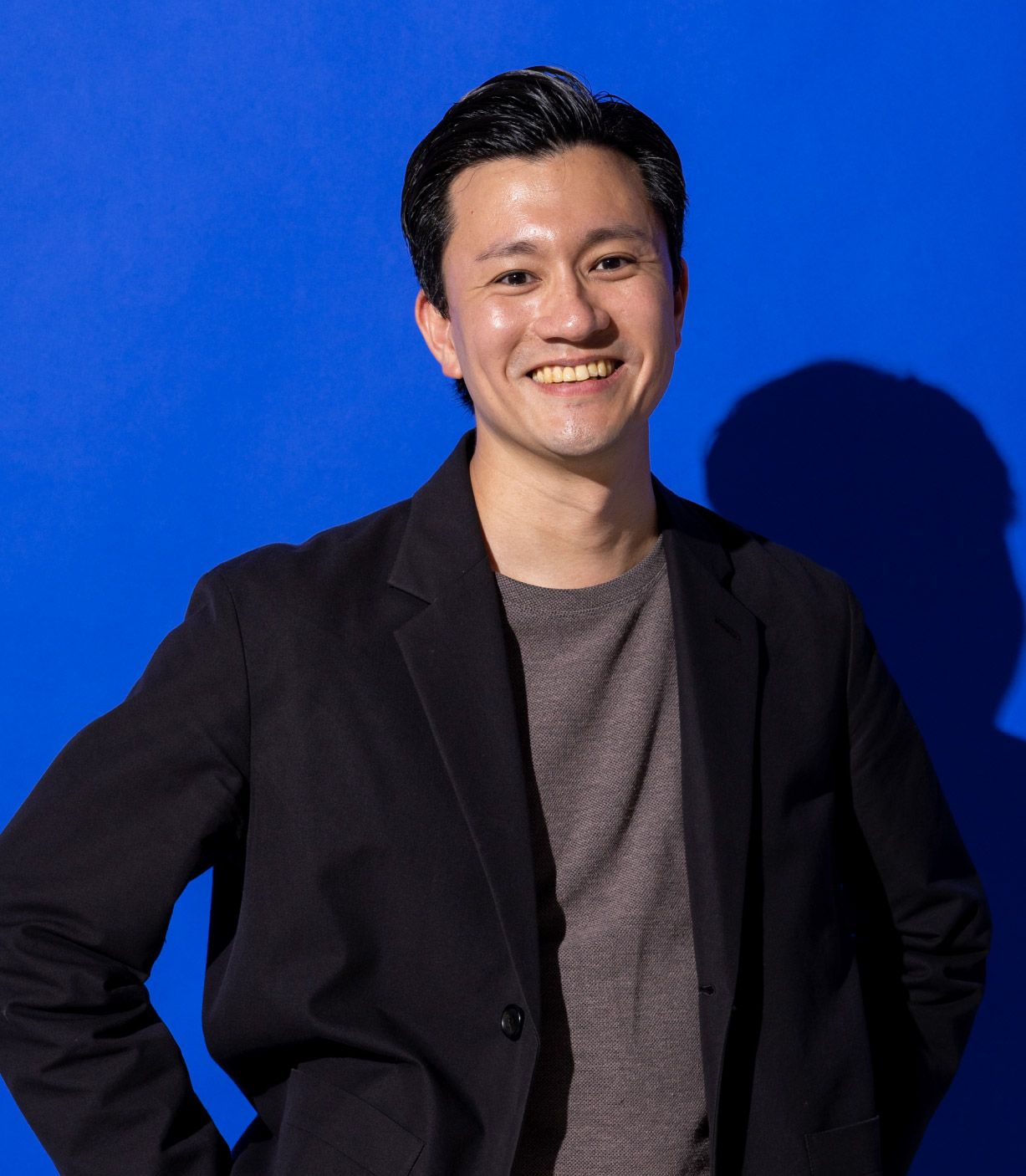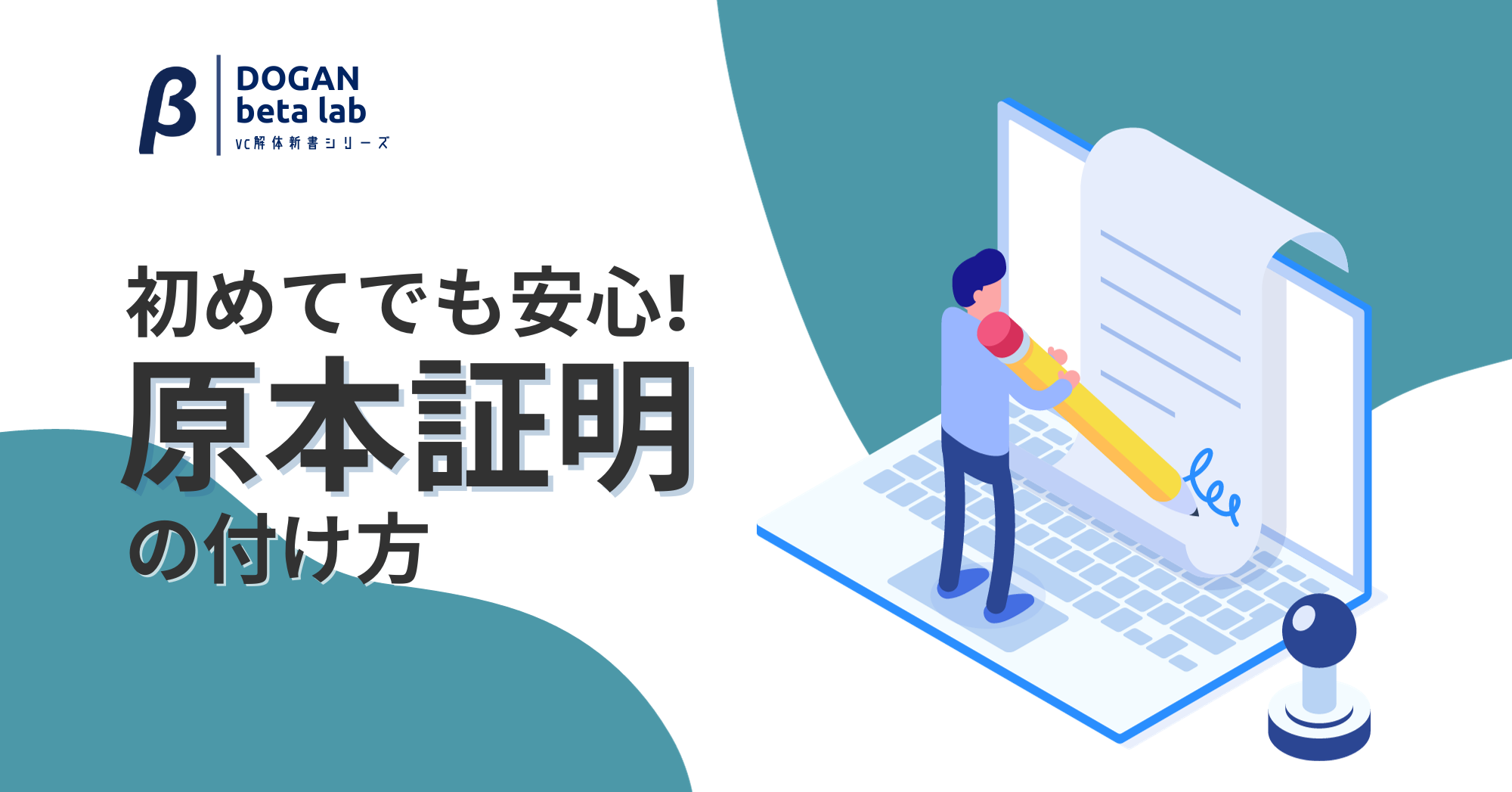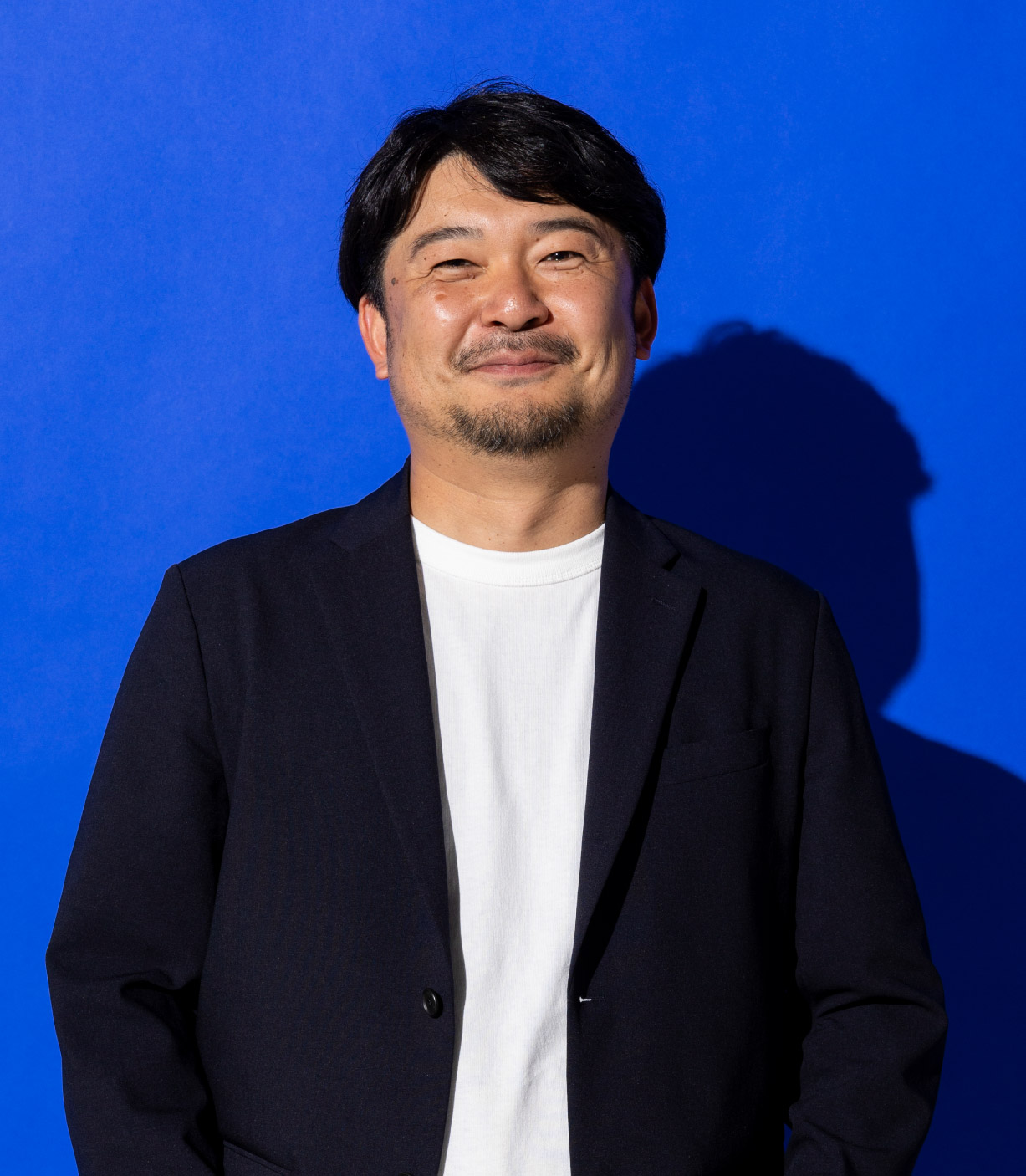Column
コラム
βventure capital Colum
地域からPMFを実現したfind──JR九州との出会いが切り拓いた「落とし物が必ず見つかる世界」への道筋


東京のスタートアップが地域の根深い課題にアプローチし、現地の企業とともに地方でPMF(プロダクトマーケットフィット)を実現する──。こうしたスタートアップの成長モデルが、今後さらに広がっていくかもしれません。
「落とし物が必ず見つかる世界へ」をビジョンに掲げるfindは、2023年5月の京王電鉄へのサービス提供を皮切りに、急速に成長を続けているスタートアップです。2025年8月時点における契約企業数は大手を中心に30社を超え、ARRは3.7億円を突破。既に導入が決まっている案件も含めると、その規模は4倍以上(約15億円)になります。
そんな同社の成長の起爆剤となったのが、京王電鉄に続く案件となったJR九州とのプロジェクトです。関係者が口を揃えて「最初のミーティングの時点で、(課題に)明確に刺さった感覚があった」と話すプロジェクトがどのように始まり、形になっていったのか。
ベータ・ベンチャーキャピタル代表取締役パートナー林龍平が、findの創業背景から地方でのPMFに至るまでのストーリーを聞きました。インタビューに協力いただいたのは、find共同創業者でCOOの和田龍氏、2025年4月にJR九州からfindに加わった坪山正史氏です。

㈱エムティーアイにてスマホアプリの企画に従事後、同社新規事業として㈱カラダメディカを立ち上げ、代表に就任。その後Automagi㈱にてAI戦略事業をリード。2021年12月に㈱findを高島と共同創業、同社取締役COOに就任。

2010年4月にJR九州へ入社。駅業務や熊本地区の企画計画部門を経て2019年4月に福岡本社の営業部に着任。西九州新幹線開業やBPR施策などの駅体制や要員計画を担当し、2023年のfind導入ではプロジェクトリーダーとしてシステム切替やfind chat内製化を実行。その後、インバウンド業務を経験し、2025年4月に九州担当として㈱findへ転職。

偶然辿り着いた「落とし物」という事業テーマ
林 : findの創業経緯から伺います。共同創業者である高島さんと和田さんは前職時代から接点があったそうですね。
和田 : 私の前職のAIベンチャーにオリックスさんが出資を検討していて、その時に私がAIベンチャー側、高島がオリックス側の担当者だったんです。一緒にオリックスさんのお客様を訪問をしたり、食事をしながら意見交換をしたりする中で意気投合し、いつか一緒に事業をやりたいという話になりました。
林 : 具体的な事業アイデアがあって起業したわけではなく、まず一緒に創業するという思いが先にあったわけですね。
和田 : おっしゃる通りです。そのため2020年からの約1年は事業テーマをひたすら模索する日々でした。富裕層の食事会にワインをデリバリーするサービスや、海外に行った時にサーフガイドとマッチングできるサービスなど、数々のアイデアを検討しましたが、なかなか人生を賭けられるテーマが見つかりませんでした。
転機はある時、高島が酔っ払ってスマホやカバンを落としてしまったことです。その翌日、彼から「各所への問い合わせや手続きがものすごく大変だった」という電話がかかってきました。考えてみると、落とし物の課題を解決できるようなクリティカルなサービスは見当たらない。これは事業になるかもしれないと二人の意見が合致し、落とし物をテーマにすることに決めたんです。
林 : 創業者が体験した強烈な課題を解決するために作ったというのが良いですよね。テーマが決まったのはいつ頃のことですか?
和田 : 2021年の夏頃です。当時、ちょうどJR東日本スタートアップさんがアクセラレータープログラムを募集していました。僕と高島には「落とし物は鉄道と密接につながっているはずだ」という仮説があったため、このプログラムの締切に合わせて2021年12月1日に会社を立ち上げました。
林 : アクセラレータープログラムをきっかけに会社を登記し、そこで最初の仮説検証を行ったわけですね。
和田 : いえ、実は書類選考で落選しました。「落とし物で何かやります」という思いだけで、具体的な事業プランやプロトタイプも存在しない状態でしたから、先方の求めている条件に合致しなかったのだと思います。さらに言うと、落とし物業務の現場を知るためにJR東日本さんのアルバイトにも応募しましたが、こちらも面接で落ちているんです。
林 : JR東日本スタートアップさんとは今年資本業務提携を締結していますし、JR東日本さんは2026年4月からサービスの導入が決まっていますよね。まさかそんなエピソードが隠されていたとは知りませんでした。
京王電鉄の現場で見つけた事業機会
和田 : 当時の私たちは落とし物という課題にはものすごく大きな可能性があると確信していましたが、具体的な事業に落とし込むにあたって「誰にどんな価値を提供できるのか」が全く見えていませんでした。
そこで落とし物についての解像度を高めるために、様々な角度から検証することにしたんです。例えばゴルフ場には落とし物が多いと聞いたので、数百社のゴルフ場に連絡をして落とし物を回収させてもらえないか交渉したり。成田空港で海外からの観光客の方にインタビューをしてみたり。そんな試行錯誤の期間が半年ほど続いた時、私たちにとって転機となる出会いがありました。
林 : 最初の実証実験のパートナーでもある京王電鉄さんですね。
和田 : はい。何をやるかすら決まっていない段階でしたが、先方の担当者の方が「今の技術を持ってすれば落とし物が必ず見つかる世界を実現できる」という私たちの思いを聞いてくれて。「良かったら落とし物管理の現場を見てみてはいかがですか」と声をかけてくださったんです。
明大前駅にある京王電鉄さんの「お忘れ物取扱所」では、20人ほどのスタッフさんが毎日大量に届く落とし物の対応をされています。実際に現場で働かせていただいて感じたのは、その作業がものすごく大変そうだということです。
前職のAI会社での経験から、登録した写真をAIで解析する仕組みを作ったり、電話ではなくLINEのチャットを用いることで、業務がもっと円滑に進むのではないか。そんな絵がパッと思い浮かびました。
その構想を担当者の方に提案したところ、「ぜひ実証実験をしてみたい」と言っていただき、2022年8月からサービスの開発が始まったんです。

林 : 私が高島さんと初めてお会いしたのが同年の10月でした。まさに京王電鉄さんとの実証実験に向けた準備を進めているタイミングだったことをよく覚えています。当時は並行して資金調達にも着手されていたんですか?
和田 : 役割分担として主に高島が投資家の方々に話を聞いていただいていましたが、林さん以外の方の反応は芳しくありませんでした。「落とし物で事業なんて信じられない」という反応も珍しくありませんでしたし、落とし物をテーマにするとしても、「AirTag」のように落とし物自体を防止するようなプロダクトの方が良いのではないかとフィードバックをいただくこともありました。
林 : すでに複数人の投資家と会っていたからこそ、私がお話を聞いた段階では計画が磨かれていたのだと思います。新規投資の場合は60分では時間が足りないことも多いのですが、高島さんの場合は30分で大半のことが聞けてしまうくらい、プランが洗練されていました。
findの構想は自分自身でも使ってみたいと感じましたし、「ぜひ九州でやってほしいな」という気持ちが芽生えたので、JR九州さんと西鉄さん、福岡市地下鉄にご連絡したんです。これは福岡のエコシステムの良いところだと思うのですが、大抵の会社には誰かしら1人は顔見知りの方がいらっしゃるので、すぐに相談ができます。とはいえ、担当者の入れ替わりなどもあって、JR九州さんはライトパーソンが思いつかず、いきなり担当役員の方に直接ご連絡を試みたのですが…。
「刺さっている音」が聞こえたJR九州との初回面談
林 : そのJR九州さんとは、2週間後にオンライン面談が実現しましたね。私も同席しましたが、はっきりと「刺さっている音」が聞こえた気がしたくらい、担当者の方々の反応が良かったことを覚えています。坪山さんはまさにJR九州側の担当者の一人として、その場にいらっしゃいました。
坪山 : 懐かしいですね。当時は営業部企画課に所属していて、遺失物業務も担当していました。林さんがおっしゃるように、findの構想はまさに私たちがずっと悩んでいた課題を解決するものだったので、和田さんのお話を聞いて全員が「これだ」と思ったんです。
当時JR九州では人手不足という慢性的な課題に加えて、コロナ禍で収益面のダメージが大きく、鉄道部門でも収支改善が急務となっていました。コロナから回復しても、できるだけコストを削減し、持続可能な鉄道事業を創造していかなければならないという課題感は強くて。その一環で、駅の電話を北九州のコールセンターに集約し、お忘れ物の専用ダイヤルの体制も見直しました。
ところが、想定以上にお忘れ物のお問い合わせ件数が多かったんです。九州中から問い合わせが殺到するので、1日あたり1000件程度の電話がひっきりなしにかかってくる。7〜8人がかりでも200〜300件対応するのがやっとでした。
林 : 応答率が20〜30%というお話でしたよね。お客様からすると、そもそも全然つながらない。
坪山 : おっしゃる通りです。運よくつながっても、口頭のみのやり取りが続くので、コミュニケーションに時間がかかるんです。例えば「黒い財布」と言われても、その情報だけでは具体的なイメージが湧きません。当時使っていたツールは写真なども登録できなかったため、文字情報のみで落とし物を特定する必要があり、精度にも課題がありました。
「時間をかけて電話したのに結局見つからない」ということでお客様からご意見をいただいていたことに加え、電話対応をしているスタッフもすごく疲弊しているのがわかっていたので、何とかしなければならないと危機感を持っていたんです。
林 : 人手不足が加速する地方だからこそ、この課題がより深刻なのかもしれませんね。当時find以外のツールも検討はされていたんですか?
坪山 : 他社のシステムや内製化も含めて検討していました。ただ写真を添付できるだけでは電話の応答率の課題が残ったり、内製化の場合はメンテナンス面の負担が大きかったり、全部の課題をうまく解決できる手段が見つけられてなかったんです。
そんな時に高島さんと和田さんの提案を聞いて、この世界観やプロダクトが実現できれば、私たちの悩みも解消されるだけでなく、お客様や社会課題の解決にもつながると感じました。何よりすごくわかりやすいプロダクトだったので、理解するのに全く時間がかからなくて。会議が終わった時点で、私たちの中では「find一択」という雰囲気でした。
特に印象に残っているのが、後日、決裁者の部長にfindの説明をした時のことです。「こんなに分かりやすくて良い提案は久々に聞いた。絶対導入しよう!」と言われてすごく驚いたことを今でもよく覚えています。
林 : 私もJR九州さんとのプロジェクトを見ていて、βとしても絶対に投資をするべきだと確信しました。これからの時代、落とし物に対応するためだけに人を採用するということはどんどん難しくなってきています。特に地方はその課題が先行している部分があると思うんです。このような取り組みこそ、自分たちが投資をする意義があると感じました。
実は投資委員会の資料もものすごく作りやすくて。JR九州さんとのプロジェクトを引き合いに出しながら、「落とし物に対応する人がいないという大きな地域課題の解決」というワードを多用しました。

博多4ヶ月滞在で見えた現場の課題とfindの未来
林 : 京王電鉄さんとJR九州さんとの実証実験が決まって、当面は営業を止めて開発に集中するというスタンスだったのでしょうか?
和田 : まだプロダクトができていない状態でしたが、実証実験をやりたいと回答をいただいたからには「やるしかない」という雰囲気でした。この2つのプロジェクトを成功させることが、中長期の成長のためにも絶対に重要になるはず。他社への営業に力を入れるのではなく、この2社に全力を尽くすという決断をしました。
JR九州さんとの取り組みでは、約560箇所の駅で同時にサービスを導入いただく計画でした。「プロダクトも実績もない状態で正気の沙汰ではない」と自分でも思いますが、落とし物の特性上、全ての駅が連携しないと効果が見えないため、一気に進める必要があったんです。
そこで何かトラブルが起きてもすぐに対応できるように、博多に4ヶ月滞在することを決めました。当初はビジネスホテルで寝泊まりしようと思っていたのですが、その話を聞いたJR九州の役員の方が心意気を買ってくださり、研修制度を活用して社員寮を使わせていただくことになったんです。
林 : 一連のエピソードがすごくダイナミックですよね。でも確かにJR九州さんとしても、まだ形のないプロダクトを全線で導入するということで、不安もあったのではないかと思います。
坪山 : 当時他のプロジェクトにも携わっていたこともあり、余計に不安があったというか、ドキドキしていました。ただ上司からも「任せる」と言われていたので、和田さんと一緒に走りながら最適なやり方を決めていくしかない、という感じでした。
和田 : 坪山さんと一緒に様々な駅を訪問して勉強会を開いたり、現場の方々のご意見を伺ったりしていたのですが、JR九州さんがすごいのが、坪山さんにかなりの権限を渡されていて。勉強会をすると「この部分はどうなるんですか?」「これはどうしたらいいでしょうか?」といった質問がいくつも出るのですが、そのほとんどを坪山さんがその場で決断していたんです。
findの細かい機能もそうですが、JR九州さんでfindを使う際のルールもこの4ヶ月の間に現場でどんどん作り上げていった感覚があります。
坪山 : 通常、私がいる部署から勉強会をすると伝えても、現場の反応はあまり良くないことが多いんです(笑)「また本社からややこしい話がきたんじゃないか」と。
ところがfindについては「ずっと課題感を持っていたので、待ってました!」という声ばかり。当然スタッフも新しいツールの使い方や業務フローに慣れる必要があるのですが、九州中を回ってもネガティブな発言をする方はほとんどいませんでした。

和田 : 当時は京王電鉄さんとの実証実験が始まったタイミングだったので、完成品ではないものの一部の機能はできていました。そこで実際に動くものを用いて説明したところ、現場のニーズにフィットしていたみたいで、すごく印象が良かったんです。
4ヶ月の間だけで現場の方から何度も「助けてください」と言われるくらい、本当に大きな悩み事だったんだと再認識するとともに、JR九州の方々にはしっかりと使ってもらえそうだと手応えを得られました。
またこれはJR九州さんに限った話ではないな、とfindの未来に対して自信を掴めるきっかけにもなったと感じています。
電話問い合わせ8割減──数字で証明されたfindの可能性
林 : 実際にサービス開始後、明確に変化が出たんですよね。find自体もそこから破竹の勢いで広がっていった印象があります。
坪山 : まず「find chat(落とし物専用のお問い合わせチャットサービス)」の運用がスタートすると、お忘れ物に関する問い合わせの電話件数が8割減ったんです。1日に1000件程度だったのが200件ほどに減ったので、応答率、さらには落とし物が見つかる確率も大幅に向上しました。電話の場合、どうしてもお客様とスタッフの間でコミュニケーションエラーが発生しますし、テキストだけのデータから探すことになるので、10件中1件見つかるかどうかだったんです。
現場から「待ってました」「助かりました」という声があっただけでなく、お客様からもチャット上で「すごいサービスを入れてくれた」とお褒めの声をいただきました。
中でも1番嬉しかったのが「またJR九州に乗ります!」というお言葉ですね。今までは不便な体験だったはずの落とし物が、プラスの体験になっていくような感覚でした。
和田 : 私たちの中では、初期のお客様である京王電鉄さんとJR九州さんが「findに価値を感じて、他の会社にも紹介してくれる」段階まで行けたら、PMFを達成したと言えると考えていました。
実際に当時JR九州さんの取り組みを知った様々な企業が、博多駅に視察にきていたんですね。そこで坪山さんが「findが現場を変えていて、お客様からも喜ばれている」ということを必死に伝えてくれていて。その姿を見てPMFをクリアしたと判断し、一気にfindの拡大に踏み切りました。
坪山 : これはJR九州に限った話ではなく、多くの鉄道会社や交通事業者も同じ課題を抱えているはずだと考えていました。findを導入すれば必ず解決できるはずだと身をもって感じていたので、本当に自分ごとと捉えて説明していた記憶があります。
「JR九州の担当者」から「findの一員」へ
林 : その坪山さんが、今やfindの一員になっているというのが感慨深いですね。
坪山 : find導入のプロジェクトが落ち着いたタイミングで、自分の今後のキャリアについて整理してみたんです。その時に、ふと「このfindを広げるという仕事こそ、自分がやるべきことなんじゃないかな」と思い始めました。
一方でfindは取引先ですから、そこに転職するというのはタブーだという認識もあり、ものすごく葛藤がありました。それでも、40歳を手前にして、新しいところに飛び込んでいくのはこれがラストチャンスになるかもしれない。そこに挑戦してみたい気持ちが上回ったので、まずは和田さんに自分の考えを打ち明けたんです。
和田さんも喜んではくれたのですが、やはり会社同士の関係性もあるので、しっかり考えましょうということでその日は別れました。ただ、私自身の思いはすでに決まっていて、その後に妻を説得し、上司にも正式に相談しました。その際には「決断が早すぎるので、少し落ち着いて冷静に考えてみたらどうか」と言っていただいたんですね。
林 : そこで一度は思いとどまったわけですね。
坪山 : はい。冷静になって考えるための環境も準備してくれ、その後は別の部署でインバウンドの仕事を担当することになり、しばらくはその業務に打ち込んでいました。
でも、どうしても心の中でfindへの転職を諦めきれない気持ちがずっと残っていました。JR九州という会社も仕事も人も好きだったのですが、findを自分の手で広めたい、社会課題を解決したい、という気持ちを諦めきれず、2024年の終わりに再び会社に気持ちを伝えました。「そこまで決意が固いなら、頑張っておいで」と送り出していただき、2025年の4月からfindで働いています。
地域から始まる「落とし物が必ず見つかる世界」
林 : 高島さんと和田さんの体験が導入企業で働く方々やエンドユーザーの人たちへと広がり、その輪が大きくなっていく様子を側で見ることができているのは投資家冥利に尽きると感じています。
JR九州さんの取り組みが発端となり、西鉄さんでも今年からfindの運用が始まりました。findが九州において注目される存在になり始めている中で、九州や福岡と関連して今後挑戦したいことはありますか?
和田 : 私たちが掲げる「落とし物が必ず見つかる世界」を実現するには、findのサービスを様々な場所で使っていただく必要があります。現在中心となっている大手企業だけではなく、自治体や警察、さらには個人が経営する飲食店など、あらゆる人たちに活用いただくことで、初めて私たちが目指す世界観に近づくんです。
それを踏まえると、特にDXへの投資をいとわない自治体など主要なプレーヤーが集約している福岡市は、理想的なスタート地点だと考えています。福岡から落とし物が必ず見つかる世界のスタートを切りたい、という思いは強いです。
林 : JR九州さんのお話でも出てきましたが、鉄道会社でも、警察や自治体でも人材不足の課題感は地方こそより深刻です。落とし物の対応も重要な業務の一つではあるものの、インフラを維持したり、市民の安全を守るためにはもっと力を入れてやらなければならないこともあるはず。findを起点としたDXの推進によって、担当者の業務負荷が減り、落とし物も必ず見つかるようになる状態はみんなにとって理想的ですよね。
私自身、行政とのコラボレーションによって、この世界観が実現できるという手応えを感じていますし、JR九州さんとの会議で感じた「findが刺さっている感覚」というのも、まさにこういうことなんだろうなと思ってるんです。
この体験をもっと広げていきたいですし、私たちも投資家として、その一助になれればと考えています。

関連コラム
-

“地元企業との連携”で事業拡大、累計35万人が活用「チャリチャリ」の地域に根ざしたサービスの作り方
- インタビュー
2018年2月に福岡でサービスを開始したシェアサイクルサービスの「Charichari(チャリチャリ)」。現在では約2,500台の自転車と500ヵ所以上の駐輪ポートを展開し、地域密着型のモビリティサービスとしてさまざまなシーンで使われるようになっています。 対象のエリアも少しずつ拡張していて… -

いまさら聞けない?原本証明の付けかた
- ノウハウ
あけましておめでとうございます! 昨年は一記事も寄稿できなかったドーガン・ベータの津野です。2024年はスタートアップの皆様に役立つような情報の発信を行っていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします! さて、ベンチャーキャピタルや銀行からの資金調達において、投資や融資の実行に必要な書類… -

事業成長マイルストーンから考える、シード資金調達時の資本政策
- ノウハウ
皆さんこんにちは。ドーガン・ベータ代表の林です。本日は、起業家をはじめスタートアップファイナンスにかかわる皆さんとぜひ議論を深めたいなと思っていた、資本政策(Capital Plan)についてのお話をさせていただきます。 林龍平 (はやしりょうへい) @betaromeo3 ドーガン・ベータ 代表取… -

ビジョンを描き、実現する ──ディープテック企業がスタートアップに変わるまでの軌跡
- インタビュー
「向かい風だった風向きが、変わり始めました。」 2023年12月、小型レーダー衛星(SAR衛星)の開発・製造・運用に取り組む福岡発のスタートアップとして華々しく上場を果たした株式会社QPS研究所(以下QPS)ですが、第二創業期ともいえる事業の大転換があったことはあまり知られていません。その立…